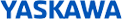安川電機のリハビリテーション製品は2022年6月に、オージー技研株式会社に製品譲渡致しました。
製品に関するお問い合わせはオージー技研株式会社にお願い致します。
対象製品
下記の通り
・上肢リハビリ装置 CoCoroe AR2
・前腕回内回外リハビリ装置 CoCoroe PR2
・足首アシスト装置 CoCoroe AAD
問合せ先
オージー技研 株式会社
本社 〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7
東京本社 〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング四階
平日受付コールセンター
(9:00-17:00):0120-01-7181
休日受付コールセンター
(9:00-17:00 ※土日祝、年末年始専用):0120-33-7181
〈ホームページ〉http://www.og-wellness.jp